
8月2日から7日にかけて開催される『青森ねぶた祭』は、1980年に国の重要無形民族文化財に指定された伝統ある夏祭りである。迫力ある大型ねぶたを一目観ようと、毎年200万人以上もの観光客が訪れる。企業や団体からの依頼を受け、何十人ものスタッフを指揮して精魂込めた大型ねぶたをつくりだすのが、『ねぶた師』と呼ばれる職人である。『紙と灯りの造形』としてのねぶたの可能性を追求する、ねぶた師の竹浪比呂央(ひろお)さんを訪ねた。

東北地方で行われる七夕行事のことで、『眠た流し』『眠り流し』とも呼ばれる。諸説あるが灯籠流しが起源とされ、灯籠自体のことも『ねぶた』という。青森県内だけでも40を越える地域で行われており、青森ねぶたと弘前ねぶたは全国的にも有名である。特に『青森ねぶた祭』は、仙台の七夕祭、秋田の竿灯祭と並んで東北三大祭のひとつに数えられている。
「青森の子ども達は絵を描くとき、アニメやヒーロー戦隊のキャラクターより、ねぶたを描くんですよ」。1959年、青森県西津軽郡木造町(現在のつがる市)に生まれた竹浪さんも、小学校1、2年生の頃からねぶたの絵を描き、針金を曲げて小さなねぶたをつくっていたという。大学生のときにねぶた師・千葉作龍氏の下で働くことを許され、毎年制作に携わったが、卒業後は薬剤師として働く道を選んだ。
しかし、大好きなねぶたはやめられない。就職後も制作を続けていた竹浪さんが29歳のとき、転機が訪れた。「自分の作品を発表するチャンスが与えられたんです。そしてありがたいことにある程度、評価をいただけたんです」
ねぶた師としてデビューを果たし、翌年から毎年制作を続けることができた。けれども、さらに制作発表の場を広げていきたいという想いが強く、35歳のときに常勤の仕事を辞め、ねぶた師として食べていく決意をしたという。ねぶたへの情熱を理解していた家族や親戚は納得したが、多くの人には心配されたそうだ。「馬鹿じゃないかって言われました(笑)。でも自分の手を動かして想いを作品にしていく方が自分らしいし、楽しい。小さな頃から好きだったから思いきって辞めたんです。若さもあったんでしょうね」
その後、2台目の依頼も請け負うようになり、展示用オブジェの制作も始めた。海外での発表、有名アーティストのアルバムジャケットでの作品使用、東京・目黒の『ホテル雅叙園』での展示などの実績も積んできた。今も薬剤師のアルバイトを不定期で続けているというが、紙と灯りの造形作家としても知られるようになっている。
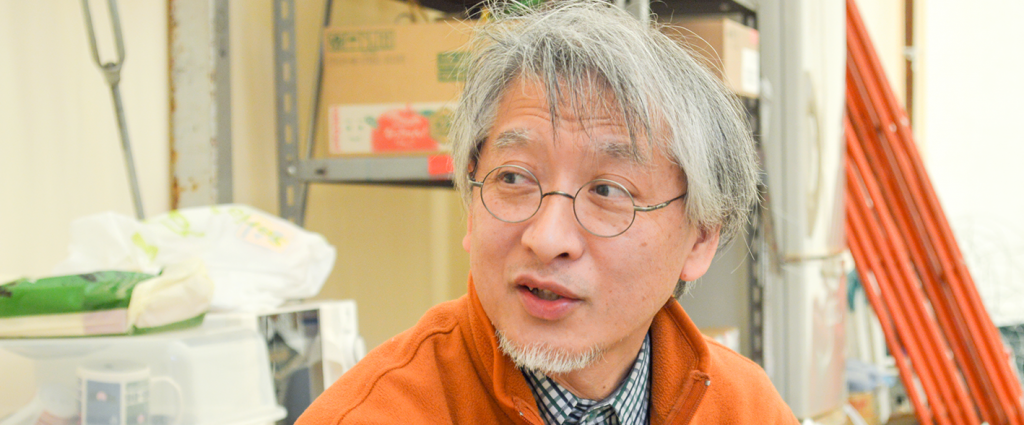
かつては「ねぶた師」という言葉はなかったという。元々は町内で文化祭のようなノリでねぶたをつくっていたが、祭りの規模の拡大とともに制作技術が高まった。腕の立つ者が大型ねぶたの制作を請け負うようになり、いつしかねぶた師と呼ばれるようになったそうだ。現在は企業または団体がスポンサーとなり、ねぶた師に大型ねぶたの制作を依頼する。「青森ねぶた祭」で運行される約20台の大型ねぶたは、主催団体や有識者、一般公募の市民などによって審査され、様々な賞が送られる。「制作費をいただいてつくる大型ねぶたは出したいから出せるものではないんです。成績が全てではありませんが、コンテスト形式で評価されるので厳しい世界です」
大型ねぶたの出陣費用は一台約2000万円。そのうち、ねぶた師の報酬は約400万円で、大半は材料費、人件費に費やされてしまう。そのため、ねぶたが好きで才能があっても、続けられない若者がいるという。この問題解決に向けて、2010年に「竹浪比呂央ねぶた研究所」が設立された。ねぶたの技術を応用した作品やねぶたをモチーフにしたグッズの販売により、後進を育てたいと考えている。「グッズを売っていくら儲かるという話ではないんです。職業としてねぶた師が食べていけるようにしたい。夏はねぶたをつくるけど通年で創作活動をしている造形作家だよね、という認識を定着させたいんです」
より多くの人にねぶたを知ってもらい、大型ねぶたを見たい方は青森に来てもらう流れをつくろうと活動を続ける竹浪さん。「青森ねぶた祭」の経済効果が何億円もあるのに、祭りを支えるねぶた師を目指す若者が生活できないという矛盾に立ち向かっている。


ねぶたには伝統的な縛りが少ない。以前は竹で骨組みをつくり、光源はろうそくであったが、竹は針金に、ろうそくは電球に変化した。彩色の絵の具も染料系から雨に強いアクリル系のものを使うようになったそうだ。「『灯籠であること』『紙を貼りこんであること』『中に灯りがあること』以外に縛りがないんです。素材の進化に合わせて良いものが出てくれば変わっていく。それがねぶたの面白いところですね」
制作は、その年の祭りが終わったらすぐに始まる。歴史や歌舞伎、民話などを題材に構想を練り、12月頃までにスポンサーと打ち合わせてテーマを決定。テーマに合わせて設計図となる原画を描き、2月頃から顔や手、刀など細部の制作を始める。5月にねぶた小屋が設置されると、大人数のスタッフが角材で支柱を組み、針金で骨組みをつくり、配線工が数百から千個もの電球や蛍光灯を取り付けていく。現在はLEDも使われるそうだ。骨組みができたら奉書紙を貼り、ねぶたらしい土台が仕上がっていく。石膏像のような白い土台に、墨で顔や手足などを描き、パラフィン(溶かした蝋)で縁取りをして色の滲みを防ぎ、透かし模様をつける。最後に筆や刷毛、スプレーで彩色をしたら、本体の完成である。
ねぶた小屋が設置される5月からの3ヶ月間はマラソンと同じだと竹浪さんは語る。「スタートしたら、ペースを落とすことがあっても止まれない」
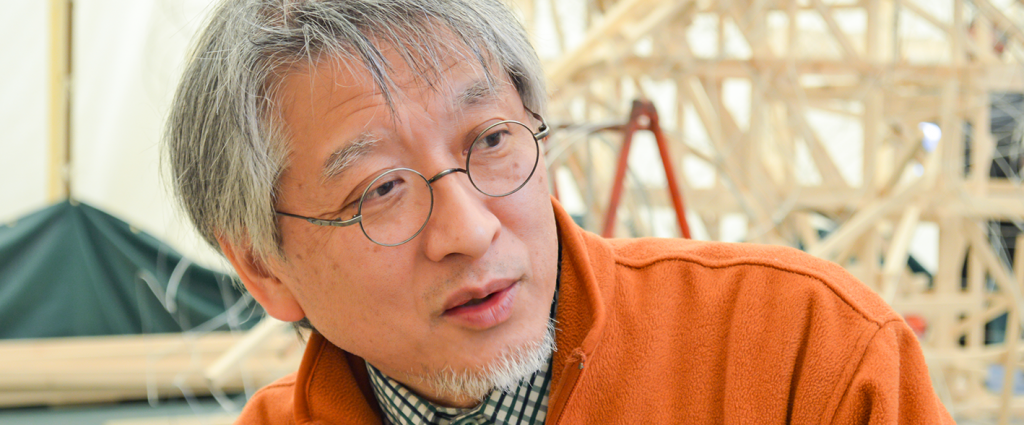

ねぶた小屋で働く人に話を聞くと、全員がねぶたへの熱い想いを語り出す。1975年生まれのねぶた師・手塚茂樹さんも子供の頃からねぶたが好きで、高校時代からねぶた制作に携わってきたそうだ。「青森の人間にとってねぶたはなくてはならない存在です。冬は雪が積もって真っ白な世界になるから極彩色に飢えているのかもしれません。もしねぶたがなくなったらどうなってしまうのか想像もできません」。手塚さんは2001年に竹浪さんに師事し、2014年にねぶた師としてデビューした。着実に活躍の場を広げながら、師匠を超えるねぶたをつくることが目標だという。
竹浪さんにとってねぶたは「生きていくための血液であり、酸素であり、エネルギーの源」だと言い切る。取材前日も今手がけている骨組みについて考え続け、当日は朝5時に目が覚めてしまったという。
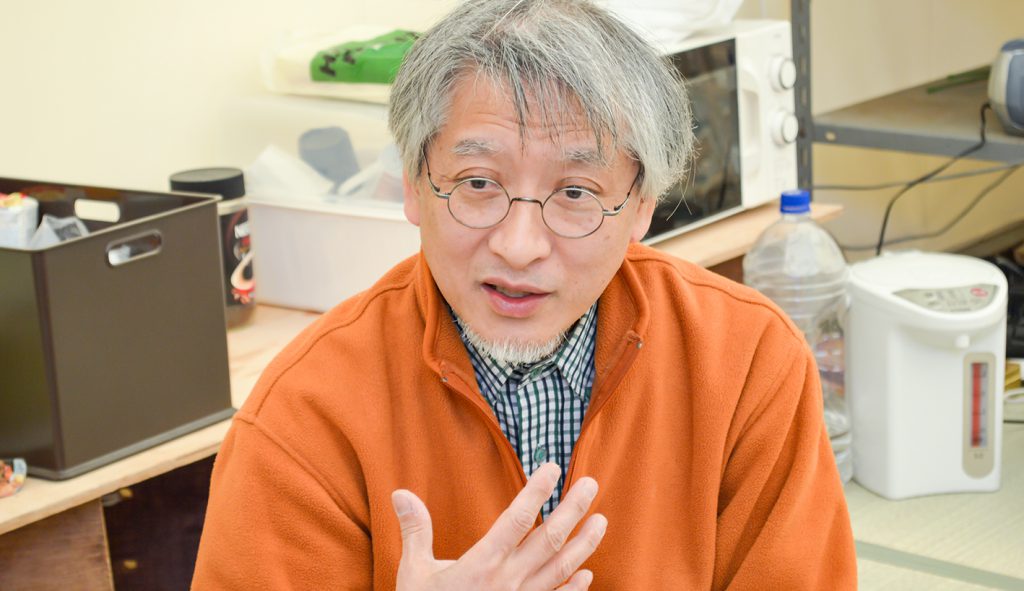
大好きなことに熱中する少年のように、竹浪さんは今年もゴールに向かって走り続けていた。


