
鋳物の町として古くから知られる埼玉県川口市。かつては多くのキューポラ(溶解炉)が建ちならび、日本の高度経済成長を大いに支えた。今は都心のベッドタウンとして閑静な住宅街が広がる。その一角にたたずむとある工房。『錫光』と掲げられた木彫りの看板には今も、時代に左右されないモノづくりを貫く職人の魂が宿る。ロクロ挽きで一点一点、手作業でつくられる錫器には、先代から受け継がれた確かな技術と伝統を守る思いが注がれている。

錫(すず)でつくられた器。日本には約1300年前に大陸から伝わったとされている。金属としては柔らかくて加工しやすく、腐食や酸化に強い性質のため、古くから重宝されてきた。一説には水を清浄に保つといわれており、酒をまろやかにし、花を美しく保つとして、酒器や花器、茶器など様々な用途に使われている。熱伝導率の高さや密閉性に富むなど、機能性も優れている。
錫器工房「錫光」は先代・中村光山(こうざん)さんによって、1987年に設立された。光山さんは15歳で錫器職人の世界に足を踏み入れ、錫工芸家、初代松下喜山氏に師事した。光山氏が手がける錫器は暮らしの中で大いに重宝され、彼の技術を買う熱心な顧客もいるほどだったという。けれども高度経済成長期以降、安価な量産品が世の中に出回るようになり、日常的に使う器としては、次第にその需要が減っていく。
光山さんが勤める工房もその影響から免れられないものとなり、経営難によって閉鎖されることとなった。光山氏は当時50歳。この際、タクシー運転手など、別の仕事へ就こうかとも考えたという。けれども多くの顧客、ファンがそれを惜しんだ。一念発起し、もとの工房の道具や機械を引き継ぎ、『錫光』として独立することにしたのだ。
息子の中村圭一さんは、当時会社員。石油化学メーカーで事務職として働いていた。父が独立した当時の様子を振り返る。「これまでずっと職人として、つくることしかしてきませんでしたから、事務仕事も不慣れで、販路拡大も難しく、苦心しているようでした」。実家の一角を改築した工房で奮起する父の様子を横目に、圭一氏は子どもの頃から『錫』というものに魅せられてきたことを思い出すようになった。
「小学校から帰ると、家には誰もいないものですから、父の働く工房へ遊びに行っていたのです。『危ないからこっちには来るんじゃないよ』と職人さんに怒られながら、傍らで宿題をしたり、合間に職人さんたちと遊んだりしていました。素材となる錫をぐにゃりと曲げてみたり、彼らがつくる錫器を眺めたり……」
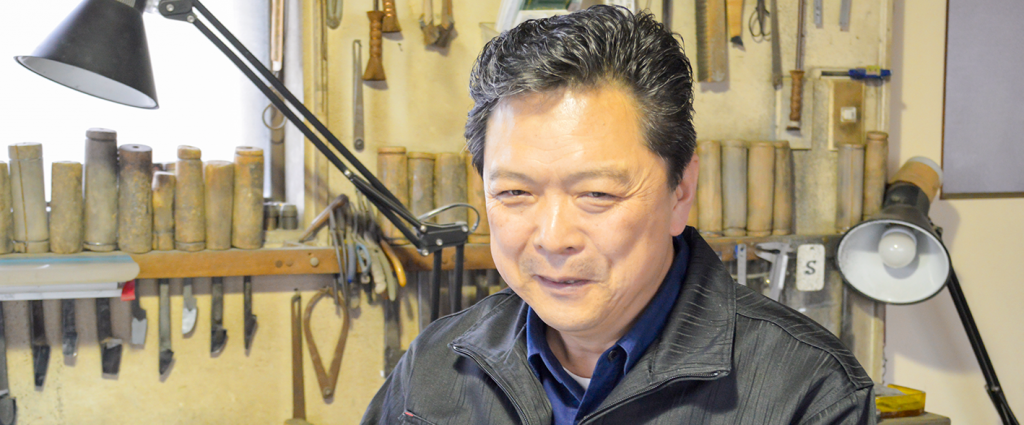
工房経営はままならずも、真摯に伝統の技を守り抜こうとする父、光山さんの姿に、圭一さんは会社に勤める傍ら、土日は工房に出入りするようになった。「はじめのうちは、あまりできることもありませんでしたけどね。道具を手入れしたり、片付けたり……。そのうち、少しずつ作業を任せてもらえるようになりました。父は多くを語るほうではありませんでしたが、『こうやるんだよ』『じゃあ、やってみて』と」。はじめて『ロクロ挽き』の作業をしてみたときには、思わず心が折れそうになったという。「回転に負けないように胸で錫器を固定して、ブレないようにグッと力を入れる。歪みなくキレイに削らなければいけないんです。まったくうまくいきそうにもありませんでした」
けれどもそんな圭一さんに光山さんは「工房を手伝わないか」と声をかける。圭一さんもまた、工房へ通うなかで知った錫器づくりの奥深さ。そして年々減っていく職人と、失われていく技術に危機感を抱いていた。自分もまた「錫器の伝統」を守る一翼を担おうと決意し、会社を辞め、正式に錫器職人として歩んでいくことにした。


錫器づくりは主に『鋳込み』『ロクロ挽き』『槌目(ツチメ)打ち』の工程からなる。まずは『鋳込み』。およそ230度という低融点の錫を溶かし、セメントでつくられた鋳型へ流しこむ。『錫光』のこだわりは、「極力継ぎ目をなくす」こと。従来、背の高い酒器や花器などは、その後のロクロ挽きの工程がやりやすいように、成型時に分割し、後からパーツを継ぎ合わせる方法をとる。けれども『錫光』では背の高いものでもそのままの大きさで鋳込みを行い、継ぎ目をつくらないようにするのだ。しかし、それゆえに続く『ロクロ挽き』の工程の難易度は高くなる。錫器の表裏を削り、内側の深いところまでカンナを届かせ、なめらかに加工していく。粗挽きから少しずつゲージを上げ、キサゲで仕上げていくと、まるで鏡のような光を放つ。歪みないまっすぐな光線が宿る。「納得のいく仕上がりができるようになるまで、どれくらいかかったでしょうかね。けれども、ロクロ挽きの具合で、たとえばタンブラーで水を飲むとき、厚みがほんの少し違うだけで口あたりも変わる」

それから『槌目(ツチメ)打ち』。錫器の側面をリズミカルに金槌で叩き、独特の紋様を描いていく。簡単そうに見えて、実は底知れなく高い技術を要する。大きさの異なる槌を器用に使い分け、まるで波紋のような鈍い光が描かれる。最近では素材の質感を活かし、鋳込みの工程だけで製品化する会社も増えてきているが、『ロクロ挽き』と『槌目打ち』という工程にこそ、職人の技が息づいていると考える圭一さんは、あくまで伝統的な錫器づくりを続けている。
もう一つ、『錫光』独自の技術が光るのは、漆による彩色。黒、ベンガラ(赤)だけでなく、青や紫、山吹など、豊かな色彩を表現している。とりわけ象徴的なのは、先代が編み出した『千歳グリーン』という緑色。青みがかった深緑は、錫器に漆を塗っては拭き取り、塗っては拭き取りを繰り返し、絶妙なグラデーションを描く。この色を使った『秋草紋水注』は、さいたま国体に来場された秋篠宮家への献上品とされる栄誉を得た。「当時すでに父は体調を崩し、床に伏せる時間が多くなっていました。私が絵付け前の工程までを担当し、できあがったものを父へ見せに行くのですが、何度も何度も『ダメ』『やり直し』と、なかなかOKが出なかった。けれども『ここまでこだわるのか』と、その妥協のない姿勢に感銘を受けたものです。絵付けは父が工房に入り、私と父の『合作』となりました。父はその半年後に亡くなり、それが最後の作品となりましたが、職人として、本当に勉強させてもらいました」


現在では伝統的な錫器を作る一方、タンブラー『COSMOS』シリーズなど、モダンなデザインを取り入れている。また、デザイナーとコラボし、ステーショナリーブランド『QUQU』を立ち上げ、錫のペーパーウェイトを製品化した。タンブラーは東京ミッドタウン日比谷1Fの『レクサス日比谷』で取り扱われるなど、新たな顧客へ錫器の魅力と可能性を伝えている。
かつて錫器は当たり前のように使われていた。今ではその良さを知る人が少なくなって久しい。「けれども、きっと実際に手に取り、使ってもらえれば、その良さをわかってもらえるはず。少し高くても、永く使え、暮らしの中に根付いていく」

圭一さんの視線は、未来を見据えている


